コマス小学校教室建設支援プロジェクト
実現に向けて大きく前進
支援金7,000ドルを送金
 |
コマス小学校教室支援のキャンペーンスタートから6月で2年になりましたが、現在、教室建設に向けて大きく前進しています。 総会時にお知らせいたしましたように、既設の教室の横に増設する形で8月末完成を目指して工事進行中です。
そのため資金面で早く支援してほしいという要望が強く、現地スタッフのジャネットさんに建設中の工事写真を送るように依頼し、その結果、建設途中の状況が把握でき、皆様からの支援金を送金することに決定いたしました。
支援金の内訳は
☆会員の皆様からの寄付
¥718,500 + 1,000USドル
☆CALOとして寄付
¥16,620
以上をドル建てに換算して合計7,000USドルの送金を6月6日に行いました。
この8月に実施される“2007ペルー活動”にて、最終的に梶田代表が現地確認をする予定になっており、早ければ落成式ができる可能性もあります。
この学校は2000年以降連続して算数ドリルと翻訳絵本を送りつづけており、正式な名称はEPM(ESCUELA PRIMARIA DE MENORES)
No.2072といいます。貧しい家庭環境の子どもが多く、かつ教室の安全性の問題で“使用禁止”を行政から言い渡された時から、ロサ校長と子ども達と子ども達の親の新たな苦労が始まりました。
ロサ校長も子ども達の親も教育に対して熱心であり、子ども達にとって教育は基本中の基本であるという考えを持っています。 もちろん、この教室の増設・環境改善により問題がすべて解決するわけではありませんが、彼らにとって非常に大きなことをやり遂げることになるとともに、その一端にかかわったCALOの会員も彼らとの絆を更に深めることができるのではないでしょうか。
次号では完成した教室の内容と子ども達の様子を写真にて詳細報告できると思います。 ご期待ください。
ペルーへ絵本輸送 テストとしてまず一箱
 どうして、「荷物を送る」という簡単なことが出来ないのか、私たちは何年もその件で「悩んで」いたのです。というのも、ペルーでは、外国からの荷物を受け取るときには税関で相当な税金を払わなければならないというのです。
どうして、「荷物を送る」という簡単なことが出来ないのか、私たちは何年もその件で「悩んで」いたのです。というのも、ペルーでは、外国からの荷物を受け取るときには税関で相当な税金を払わなければならないというのです。
そんなわけで、「翻訳絵本をペルーの子どもたちに贈る」事業を始めて以来、ほぼ毎年ペルーを訪問したそのたびに自分たちの荷物として出来るだけ大きな旅行かばんにそれらの絵本を詰め込んで運んでいました。5-6人で行けば、100冊の絵本も20冊ずつ持てばそんなに負担なく運ぶ事が出来ます。しかし、昨年のようにだれもペルーに行けない、とか、今年のように2人で行くとなれば負担は増えます。この事業を長く続けていけるためには「輸送」は必要不可欠なことと思われました。
2年程前にも「輸送」に手をつけたことがありました。しかし、途中でだめになりました。
まず、受け取りの際に税金を免除してもらうためには、受け取る学校がAPCIという許可を役所からもらっていなければなりません。つまり不正なく寄付を受け取れる学校であるという証明なのでしょう。在日ペルー大使館の話では、ペルーの国立の学校ならほとんどが持っていますよとのことでしたが…しかし、実際に現地スタッフのジャネットに調べてもらったところ、私たちが毎年ドリルを配布している6つの学校すべてがAPCIをもっていませんでした。そこでまず、その手続きから始めてもらったのです。
6つの学校の中でもいちばん学校としてよく機能していると思われる「Fe y Alegria 43」校の校長に頼んでその手続きをしてもらいました。そして、その学校宛てに絵本をつめて小包を作ります。同時に、どういうタイトルの絵本が何冊、中古であっても市場価格はいくらか、もちろん総重量はどれだけかなど詳しく大使館に報告し「寄贈レター」なるものを作ります。そしてそのレターに「査証」をもらい、「査証」つきのレターを学校に送ります。レターが届いたという知らせがあればいよいよ小包が送れるのです。「査証」があれば税関に大使館が便宜を図ってくれるというのです。
ところが、前回はその「査証」つきのレターがその学校に届かず、ちょうどペルーに行った者がそのコピーを持参しましたがオリジナルでないとだめということで、ここで「頓挫」したのでした。
今回は「査証」を学校に送らず、ジャネットの勤務先のカトリック大学に送り無事届きました。彼女がそれを学校に渡したわけです。ようやく小包の発送にこぎつけました。
果たして、その小包が届くかどうかが心配ですが、うまくいけば少々お金はかかりますが絵本輸送が軌道に乗るわけです。また報告します。
CALOの本ができました
「ペルーの子どもたちに算数ドリルを!」
― 平凡な主婦がNGOを立ち上げた ―
「CALOの歩み」をまとめました
2004年2月、CALOが設立10周年を迎えたとき、会報Amigos NO.55から「CALOの歩み」という連載を始めました。これはCALO設立時に関わった会員の熱い思いを忘れないで、新しく会員になってくれた人びとのためにもその思いや経緯を伝えるために是非書いておきたいという考えからでした。
いろいろな資料やメモ、日記などをもとにあれも書こう、これも書きたいと書き進んでいくうちに2年の歳月が経ち15回もの連載になってしまいました。そして、これを一冊の本にして、CALOの活動を一人でも多くの人に知ってもらい、活動の財政難をなんとか出来ないものかと考えたのです。
幸いにも東京の協同出版社というところが快く出版を引き受けてくださいました。本になるには15回の連載であってもまったく字数が足りません。連載を通してみなおしていくと、重複している箇所や言い足りない箇所など、やはり手を入れなおさなくてはなりませんでした。
これからNGOの立ち上げを考えている人々にも少しは役立つかもしれないと、助成金をもらった経緯なども書き足しました。私自身CALOの活動のために初めてペルーの土地を踏んで以来、9回もの訪問をしています。それに付随して活動とは関係なくたくさんの経験をすることが出来ました。そんな中で是非伝えたいことを「エピソード」という形でこの本のあちこちに書きました。モノクロですが写真もできるだけたくさん掲載してもらいました。未だ日本の人びとにとって「遠い」国である南米ペルーのさまざまな面を楽しんでいただけると思います。
しかし、何より設立以来、会員となって会費という形でずっと協力してくださっている方々に心からのお礼として本の形にして「報告」させていただきたいと思っています。
表紙の帯には大阪外国語大学教授の染田秀藤先生が推薦文を書いてくださいました。
協同出版社長から300冊の寄付
前述の協同出版社の社長、小貫輝雄氏から300冊の寄贈をいただきました。これを買っていただくと全額CALOの収入となります。
| インターネットからも購入できます http://www.nihon-bookclub.com 株式会社 日本ブッククラブ |

| 高槻東ロータリークラブ様 貴重な寄付金をありがとうございます! |
| 去る7月20日(金)たかつき京都ホテルでの高槻東ロータリークラブの例会に参加させていただきました。その際に例年のとおりCALOの「算数ドリル事業」にと寄付金をいただきました。 これは10回目であり、CALOの歩みにほぼ等しいと思えるほどです。毎年このご寄付を「当てにして」予算を組むほど頼りにしています。言い換えればこれがなければ「算数ドリルをペルーの子どもたちに」という事業は継続が困難になるということではないでしょうか。私たちの活動にとってはほんとうに「貴重」な資金なのです。ありがとうございました。 |
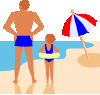 |
☆夏休みに入ったのに台風が来たり大荒れの日本です。 ☆懸案だったコマスの教室増設もなんとか完成のようでほっとしています。 ☆2年ぶりのペルーですが「孫づれ」でどうなることかと… ☆絵本輸送もあと一歩。それも確かめてこなくてはなりません。 ☆厳しい暑さのなか、皆様、どうぞお気をつけください。(M) |